
2025.08.07 卓話:RCC長瀬楽人会「矢作北小学校雅楽部の皆さんの雅楽演奏」
会長あいさつ
皆さん、暑い中お集まりいただき、ありがとうございます。
先週の夜間例会では、新入会員の方々も来てくださって、本当に嬉しかったです。これからも一緒に活動できることを楽しみにしていますので、どうぞよろしくお願いします。
先日、大阪歴史博物館で「正倉院 THE SHOW」という企画展を見てきました。奈良の正倉院にある宝物のレプリカが展示されていて、その制作技術の高さに感動しました。
中でも一番のお目当ては、本物の香木「蘭奢待」の香りを体験できるコーナーでした。正倉院の宝物と同じ時代に生まれたとされる雅楽を、本日、矢作北小学校の皆さんが演奏してくださいます。雅楽は、私たちが生きる現実を超えた、無常の世界を表現するものだと言われています。
子どもたちが奏でる素晴らしい雅楽の世界を、どうぞお楽しみください。
矢作北小学校雅楽部の皆さんの演奏








こんにちは。矢作北小学校雅楽部です。今年も呼んでいただき、ありがとうございます。
最初に、私たちの学校と雅楽部について紹介します。
私たちの学校は、今年で152年目を迎える、800人以上の児童が通う大きな小学校です。昔から雅楽が盛んな地域だったので、全国でも珍しい雅楽部ができました。私たちは雅楽の伝統を守るために、毎日練習を頑張っています。
今日は雅楽の魅力が伝わるように、二曲演奏します。短い時間ですが、楽しんでください。
最初に演奏するのは、雅楽の中で一番有名な「越殿楽」です。ぜひお聞きください。
雅楽演奏:越殿楽(えてんらく)
皆さん、雅楽についてもっと知ってほしくて、クイズを用意しました!第1問。雅楽はいつの時代から始まったでしょうか?1昭和・2平安・3江戸 正解は「2. 平安」です。雅楽は、平安時代に日本で独自の音楽として完成しました。1200年以上の歴史があるんですよ。第2問。この楽器は何でしょう?正解は「3. 鉦鼓」です。
他にも色々な楽器があります。
龍笛(りゅうてき):美しい音色で曲を彩ります。
篳篥(ひちりき):歌声のような主旋律を演奏します。
笙(しょう):唯一和音を奏でる楽器です。
鉦鼓(しょうこ):高く澄んだ音色で音楽を引き締めます。
楽太鼓(がくたいこ):力強い音で音楽に厚みを生み出します。
鞨鼓(かっこ):演奏の速さを決める、とても大切な楽器です。
これらの楽器の音が重なって、美しい雅楽の曲ができあがります。最後に、私たちの大好きな「抜頭」という曲を演奏します。リズミカルで楽しい曲です。ぜひお聴きください。
雅楽演奏:抜頭(ばとう)
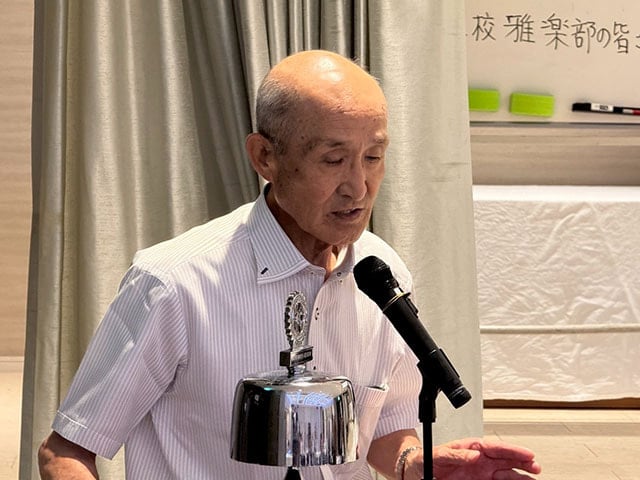
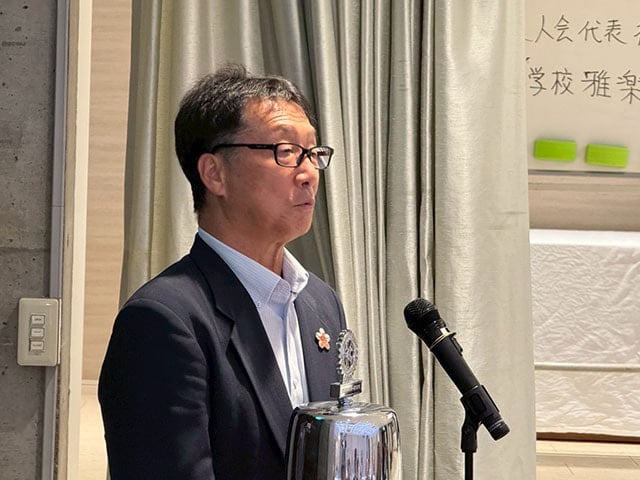


長瀬楽人会代表 杉山雄二様卓話
この度は岡崎東ロータリークラブの例会に、長瀬楽人会と矢作北小学校雅楽部をご招待いただき、誠にありがとうございます。また、日頃から長瀬楽人会にご支援ご協力いただいていること、心よりお礼申し上げます。
長瀬楽人会は年間12?13回、主に神社やお寺で演奏活動を行っています。今年は5月に京都で開催された親鸞聖人の誕生を祝う「宗祖降誕会」、雅楽「献納会」に参加し、全国から集まった29団体とともに盛大な演奏会を経験しました。
今後の予定としては、11月16日と17日に願照寺にて稚児行列に参加し、演奏を披露する予定です。午後には例年通り雅楽演奏会も開催します。
現在、20代から高齢者まで幅広い世代のメンバーで活動していますが、人材確保が課題です。そこで、毎年秋に神社の例大祭で演奏会を開き、幅広い世代の方々に雅楽の魅力を知っていただくことで、新しい仲間を募っています。おかげさまで少しずつ新しいメンバーも増え、活動も良い方向に向かっています。
また、私たちは矢作北小学校雅楽部の支援も行っています。平成元年に発足して以来、約36年間活動を続けており、全国的にも小学校の雅楽部は大変珍しい存在です。これは、学校長や顧問の先生方、そして保護者の皆さんのご支援のおかげで成り立っています。
最後に、岡崎東ロータリークラブの益々のご発展と、本日ご出席の皆様のご健康とご多幸を祈念し、私の挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。
矢作北小学校校長 細井鶴貴様ごあいさつ
『矢作北小学校』のこの雅楽部が本当に全国的に珍しい貴重な部として、そして、岡崎市としても続けていくべき文化的にも貴重な体験のできる部として、これからも存続をしていかなければならないということを本当につくづく感じております。本当に『岡崎東ロータリークラブ』の皆さま、そして『長瀬楽人会』の皆さまの支援のもと、こうしてこういった機会をいただけること本当に感謝しております。
練習を見ておりますと、日に日に上手になっていく子どもたちで、特に今日は衣装を纏うと立ち居振る舞いも、その昔を思い起こすような、日本的な姿になっているというのを感じて、子どもたちの成長を本当にうれしく思いました。これからもこの伝統を引き継いでいきたいと思っております。
今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。


